【発達障害のある子との家庭での関わり】毎日の積み重ねが、子どもの未来を育てる
更新日:2025年6月29日

はじめに:その子らしさを、家庭が受け止める
発達障害のある子どもと過ごす日々は、時に想像を超える大変さを伴います。でも同時に、他の誰よりもその子の“らしさ”に気づけるのは、毎日一緒にいる家族です。
自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)など、多様な特性を持つ子どもたちは、それぞれ独自の世界で生きています。この記事では、家庭の中で親ができる関わりや支援、日々の心がけ、そして親自身のメンタルケアについてご紹介します。
まずは「違いを理解する」ことから
子どもが何かしらの“困りごと”を抱えている場合、それは「わざと」ではなく「特性」から来るものです。例えば——
- 音や光に過敏で、集中できない
- 急な予定変更にパニックを起こす
- 相手の気持ちを読み取るのが苦手
これらは、本人にとって“生きづらさ”そのものです。親がまず特性を正しく理解し、行動の背景を知ることが、安心できる家庭環境づくりの第一歩です。
家庭でできる具体的な関わり方
1. 「見通し」を持たせる
ASDの傾向がある子どもは、突然の変化に対する耐性が低いことがあります。そこでおすすめなのが、スケジュールの視覚化です。イラストや写真を使った「視覚支援ボード」を使うことで、安心感と行動の予測がしやすくなります。

2. 否定せず、肯定で返す
「またやってるの?」ではなく、「そうしたかったんだね」「ここまでできてすごいね」と言い換えるだけで、子どもの心は守られます。
3. 行動を小さく区切る
たとえば「お片付けしよう」ではなく「まずはブロックを箱に入れよう」。一つ一つのハードルを下げることで、自信と成功体験が増えていきます。
感情の共有とコミュニケーション
発達障害を持つ子の中には、言葉で気持ちを伝えるのが苦手な子もいます。「今、怒ってる」「かなしい」「うれしい」などの感情語を、日常の中で少しずつ教えていくことが大切です。
親が子どもの感情を“代弁”してあげることで、「自分の気持ちはわかってもらえるんだ」という信頼感が育ちます。

兄弟姉妹へのケアも忘れずに
発達障害のある子に親の注意が集中しすぎると、きょうだいが「放っておかれている」と感じてしまうこともあります。意識的に「その子だけとの時間」を作る、ちょっとした声かけを増やすだけでも、関係はぐっと安定します。
きょうだいが感じている不安や嫉妬も、否定せず受け止めてあげることが大切です。
親自身のメンタルを守ることも「育児」
夜泣きやパニック、癇癪、登園渋り……。子どもへの対応に追われる中で、自分の限界を感じる瞬間は誰にでもあります。
そんな時は「完璧な親」でいようとしないこと。誰かに頼ることは“甘え”ではなく“戦略”です。ファミサポ、児童発達支援、自治体の相談窓口、オンラインコミュニティなど、サポートは必ずあります。
ときにはスマホを置いて、深呼吸をするだけでも気持ちは変わります。まずは「親の心が元気であること」が、子どもにとって最大の安心材料です。
まとめ:その子にしかない「輝き」を見つける関わり
発達障害があるということは、あくまでも「個性のひとつ」。だからこそ、家庭の中で「安心して過ごせる環境」を整えることが何より大切です。
親が子どもの特性を理解し、できる範囲で支援しながら、時には一緒に笑い、時には一緒に泣く——そんな日々の積み重ねが、子どもの未来に確実につながっていきます。
焦らず、比べず、今日できることを1つずつ。親だからできる関わりが、今日も誰かの希望になりますように。

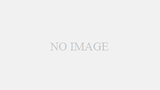
コメント