
赤ちゃんの夜泣きは、多くのママ・パパが悩む育児の壁のひとつです。日中の疲れがたまっている中、真夜中に突然泣き出す赤ちゃんに、戸惑いや不安を感じることも多いでしょう。
この記事では、赤ちゃんが夜泣きをする理由と、実際に効果があった5つの対処法について詳しく解説します。育児中の方にとって、少しでも心が軽くなるヒントになれば幸いです。
【目次】
- 夜泣きとは?
- 赤ちゃんが夜泣きする5つの主な理由
- 夜泣きの5つの対処法
- よくあるQ&A
- まとめ
1. 夜泣きとは?

夜泣きとは、赤ちゃんが夜中に突然泣き出し、なかなか泣き止まない状態を指します。通常、昼間と夜の区別がついてくる生後3〜4ヶ月以降に見られ、生後6ヶ月〜1歳ごろにピークを迎えることが多いです。
夜泣きは決して異常なことではなく、発達過程のひとつです。しかし、毎晩続くと保護者の睡眠が奪われ、ストレスや育児疲れの原因になります。
2. 赤ちゃんが夜泣きする5つの主な理由
1. 睡眠サイクルが未発達

赤ちゃんの脳や神経はまだ未発達のため、大人のように深い眠りと浅い眠りを安定して繰り返すことができません。そのため、ちょっとした刺激で目が覚めてしまい、泣き出すことがあります。
2. 空腹やのどの渇き

成長が著しい時期の赤ちゃんは、夜間にもお腹が空いたり、水分が不足したりすることで不快感を覚え、泣き出すことがあります。
3. おむつの不快感

おむつが濡れている、蒸れているなどの不快感から、眠りが浅くなり夜泣きに繋がることがあります。
4. 成長過程の変化(発達段階)

寝返り、はいはい、言葉の発達など、心身の変化が急激に起こる時期は、脳が活性化され、夜中に目が覚めやすくなるといわれています。
5. 情緒の不安定さや日中の刺激
昼間の経験(外出、人と会う、大きな音など)が刺激になり、眠りに影響を与えることもあります。特に敏感な赤ちゃんは、環境の変化に反応しやすいです。
3. 夜泣きの5つの対処法
1. 赤ちゃんの生活リズムを整える
朝は同じ時間に起こし、太陽の光を浴びさせましょう。昼間に活動的に過ごすことで、夜の眠りが深くなる可能性があります。
✔ ポイント:
- 昼寝の時間が長すぎる場合は、調整してみる
- 就寝時間を毎日一定にする
2. 寝かしつけのルーティンを作る
毎晩同じような流れ(お風呂→授乳→絵本→就寝)を繰り返すことで、「これから寝る時間だ」と赤ちゃんの体と心が準備できます。
✔ 例:
- 優しい音楽を流す
- 部屋の明かりを暗くする
- ママやパパの声で語りかける
3. 授乳・ミルクのタイミングを見直す
夜間にお腹が空いて目が覚めている可能性がある場合は、就寝前にしっかりと授乳をしてみましょう。生後6ヶ月以降であれば、徐々に夜間授乳を減らしていくステップも検討できます。
4. おむつ替え・衣類の見直し
夜中でも不快感が出ないように、吸収力の高いおむつや、季節に合った通気性の良いパジャマを選ぶこともポイントです。
✔ チェックリスト:
- おむつは就寝前に必ず替える
- 暑すぎず寒すぎない室温(20〜25℃目安)
- 肌着にタグや縫い目がないか確認
5. 親のストレスを溜めない工夫
夜泣きは親の責任ではありません。完璧を目指さず、頼れる相手(パートナー、祖父母、保健師など)にサポートをお願いしましょう。
✔ 自分を責めないために:
- SNSで他のママの声を探す
- 昼間に15分でも仮眠を取る
- 辛い時は一時保育や育児相談を利用する
4. よくあるQ&A
Q1. 夜泣きはいつまで続くの?
個人差はありますが、多くの場合は1歳〜1歳半ごろには落ち着いてきます。一時的なものなので、焦らず対応しましょう。
Q2. 抱っこでしか寝ないのは問題?
問題ではありません。赤ちゃんにとって親のぬくもりは安心感そのもの。卒乳や歩行が進むと自然と自立した睡眠に移行することも多いです。
5. まとめ
赤ちゃんの夜泣きは、成長と発達の一部であり、一時的なものです。原因はさまざまですが、生活リズムを整えたり、環境を見直したりすることで、少しずつ改善されていくことが多いです。
ママやパパが「ひとりで抱えこまない」こともとても大切です。子育てはチーム戦です。必要であれば地域の育児支援や医療機関を頼りながら、無理なく過ごしていきましょう。
筆者は双子の子育てをしていますが、パートナーと協力できるときは、互いに遠慮せず頼れる環境を作っていました。また「子育てはチーム戦」とあるように頼れる人(家族や友人)、地域資(子育てサロンなど)は惜しみなく頼っていくことで抱え込まない環境も整えることで乗り越えてきました。
この記事が、夜泣きに悩むご家庭にとって、少しでもヒントになれば嬉しいです。

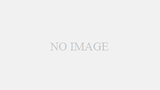
コメント